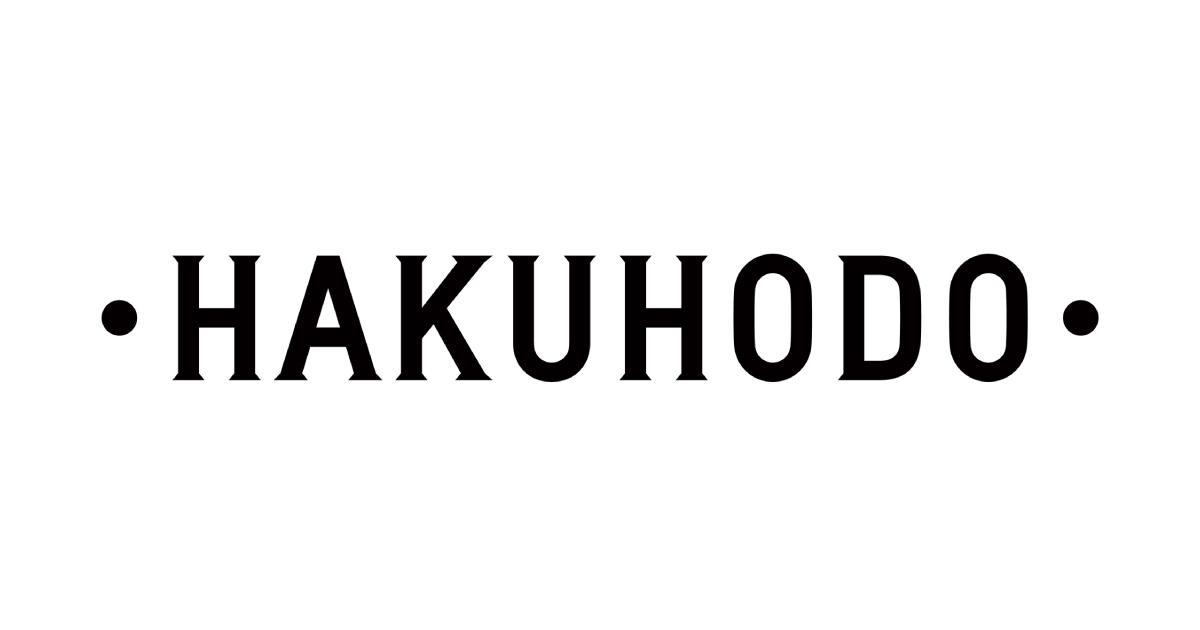中本八尋と武蔵野美術大学クリエイティブイノベーション学科3名で構成されたチームは、株式会社ジャクエツ、株式会社博報堂(UNIVERSITY of CREATIVITY)とともに、千葉県君津市に創造的な地域風土を「遊び」というテーマで探索・提案する産学連携プロジェクトを通じて、こどもたちが自由に発想したあそびを、魅力的な造形を有した遊具とパークで実現できるプレイパーク、「あそびファクトリー」を提案しました。
あそびファクトリーは、地域の方々とこどもが共創し、あそび場を作っていくこれまでにないパーク構想です。うごかせるジョイント型の遊具とジョイント型の遊具を使うパークによって、こどもたちと清和、その先のつながりをはぐくんでゆくことを目的としています。
つくってみる、あそんでみる、考えてみるといったサイクルで、こどもたちの興味を誘い、あそびとしての形を模索しました。
パークの概要
.jpg&w=3840&q=75)
パークは、やまを中心に円状に広がっていくような形状をしており、個性的で魅力的な固定型の遊具が各エリアごとに広がっています。周りに広がる「サークル」は、「つながる」ことを意識した曲線で構成され、地域の方々や保護者が、子どもが遊んでいる様子を見守りながら、ちょっとした作業や休憩を行えます。
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
パーク内は4つのゾーンに分かれている想定で、それぞれ遊び方や遊びの激しさが少しずつ異なります。
ジョイント型遊具の概要
パーク内には等間隔で穴が空いており、そこにさまざまな形のジョイントを差し込んだり、つなげたりして遊びをつくることができます。子供だけで動かすのが難しいものは大人が補助する想定です。
.jpg&w=3840&q=75)
あそびファクトリーでは、つくってみる、あそんでみる、考えてみるといったサイクルで、こどもたちの興味を誘い、あそびとしての形を模索しています。
こどもたちの興味を惹く存在として、YouTubeやゲームなどが挙げられますが、清和において、「あそびファクトリーにいきたい!!」となるような、空間設計とエコシステムについてより深めていければと考えています。
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
プロジェクトのはじまり
本プロジェクトは、武蔵野美術大学クリエイティブイノベーション学科学部3年のカリキュラムで実施されました。当プロジェクトでは、株式会社博報堂(UNIVERSITY of CREATIVITY)、株式会社ジャクエツとともに、千葉県君津市に創造的な地域風土を「あそび」というテーマで探索・模索することを題として設定されました。我々のチームは、千葉県君津市清和地区を舞台とし、清和地区に根差した地域活動などについてのリサーチから活動を始めました。
事前調査
フィールドワークを行う前に、千葉県君津市君津地区がどのような場所であるか、さまざまな情報を入手し、デスクトップリサーチを行いました。さまざまな情報を目にする中で、この広大な自然が広がる地域であるにもかかわらず、こどもたちが一堂に会することのできるような公園が存在していないことを発見しました。
.jpg&w=3840&q=75)
フィールドワーク
フィールドワークとして、君津地区に3日間宿泊しながらさまざまな地域の特徴や地域で広がっているコミュニティ活動についてリサーチしました。
(1).jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
実際に地域に住んでいる人が自分の欲しいものを作る「地頭自治」と呼ばれる活動をされている、地域コミュニティの「コミュニティ清和」の皆さんにインタビューさせていただく機会を得ることができ、清和の現状や詳しい子育ての状況などについてお聞きしました。
.jpg&w=3840&q=75)
その中でも、コミュニティ清和の若手メンバーの皆さんにお話をお聞きする中で、こどものころに人や場所との良いつながりを得ていることによって、Uターン等の地元に戻ってくるアクションを起こしていることを発見しました。
.jpg&w=3840&q=75)
また、以前清和地区に存在していた「秋元小学校」が廃校となり、新しく複合施設・コミュニティのハブとなる「おらがわ」の工事中の現場にも視察させていただきました。建設中の設備には、保育園やコワーキングスペース、公民館機能などが揃う中、6歳から17歳のこどもの居場所がおらがわでは手薄であることを発見しました。
コンセプトメイキング
このようなフィールドワークから得た発見から、私たちは清和地区にはこどもたちが地域と「良いつながり」が育める空間が必要なのではないかというアイデアを得ることができました。その中で、レゴのようにあそびがプロトタイピングできたら非常に面白いのではないかという着想を得て、これらの提案を行うこととなりました。
中本八尋は、当プロジェクトにおいてクリエイティブディレクションとプロジェクトディレクション、デザインを担当しました。